ヌーラボのリモートワークはなぜ成り立つのか?
目次

ヌーラボのメンバーは、リモートワークを基本とし、全国各地で働いています。一方で、2023年以降世の中では「オフィス回帰」の動きが広がりつつあります。それでもヌーラボがリモートワークを続ける理由とは?リモートワーク下でチームワークはどう成り立っているのか?札幌市、益田市、福岡市、北九州市で働く4名のメンバーに語ってもらいました。
中国出身、札幌在住。2023年12月にヌーラボへ入社。札幌に住みながら、海外拠点のエンジニアとも協力し、SREとしてシステムの信頼性向上に取り組む。
2022年6月にヌーラボへ入社。島根在住。開発エンジニアとして、プロジェクトマネジメントを担う。フルリモート環境を生かし、家族との時間も大切にしながら、登壇やイベントにも積極的に参加している。
2024年1月にヌーラボに入社後、福岡へ移住。マークアップエンジニアとしてフルリモート環境を生かしながら働く一方、オフィスギャザリングや社内イベントを通じてチームとの交流にも積極的に参加している。
2021年8月にヌーラボへ入社。経理課長として、リモート環境で経理業務を推進。ヌーラボ入社後、愛知県から地元・北九州へUターンし、家族との時間を大切にしながら働く。
地方でも、待遇やキャリアを諦めなくていい
ー皆さんがリモートワーク中心の働き方を選んだ経緯や理由を教えてください。
- 中道
私はもともと広島県で毎日出社する会社に勤めていたのですが、双子の育児に追われる日々でした。そこで、妻の実家がある島根県益田市に移住すれば、家族から育児のサポートを受けられると考えました。しかし移住を検討する中で調べてみると、益田市はIT企業の数が限られ、待遇も都会に比べて低くなってしまうことがわかったんです。
そこで「フルリモートなら家族との時間を増やせる上に都会と同等の待遇を得られ、レベルの高い人とも一緒に働けるはず」と考え、結果的にヌーラボへ入社し、島根に移住しました。
- 史
私は日本に来て以来、ずっと北海道で過ごし、就職後は札幌に拠点を置いて働いてきました。そして結婚して子どもが生まれ、家族の生活環境を考えるようになりました。そんな中で転職を考えたとき、家族全員が大好きな北海道からはできれば離れたくなかったため、一旦選択肢を「札幌で出社できる会社」か「フルリモート」の二択に限定してみたんです。
ヌーラボを見つけたときは「ここなら札幌に住みながら、しかも海外拠点のエンジニアとも仕事ができるかもしれない」と期待が膨らみました。実際、アメリカやオランダのメンバーとプロジェクトを進める機会が多く、地方に住んでいながら国際的なプロジェクトに携われることに面白みを感じています。
- 古田
私はもともと別の地域に住んでいましたが、実家が北九州だったので、いつかは戻りたいと思っていました。経理という仕事柄、出社は必須かと思っていましたが、ヌーラボでは「月に数回出社できればOK」という話だったので、入社後にUターンを決断しました。実際、リモート中心でも経理の業務は十分に回りますし、家族も安心させられるので助かっています。
- 榎本
私も古田さんと同じく、ヌーラボに入社してから福岡への移住を決めました。2024年1月に入社し、直後3月の全社集会(General Meeting)で福岡を訪れた際、想像以上に都会で家賃も安く、食べ物も美味しいことに驚きました。自然も近くて魅力的だなと感じて、「ここに住もう」と決めたんです。今はヌーラボの「オフィスギャザリング」などのイベントへの参加や「Small Talk」などの制度を活用しながら、必要に応じて出社もしつつ、福岡ライフを楽しんでいます。
リモートワークを成り立たせる
Backlogでの情報共有の文化
ーリモートワークではどのような課題を感じますか?
- 史
私のチームは、オランダのアムステルダムやアメリカのニューヨークの拠点のメンバーとも連携しています。時差があるので、すぐに返事が欲しいときでもタイムラグが生じてしまう。これは対面で働いていた頃にはなかった難しさですね。また、文化的な違いもあるので、各国のメンバーがそれぞれの働き方や考え方を持っていて、何気ないやりとりが思わぬ認識のずれにつながることもあります。
- 榎本
出社しているとちょっとした雑談から偶然生まれるアイデアが多いと感じています。ただ、オンラインではその機会が減ってしまうこともあり、そこがリモートならではの難しさかもしれません。とはいえ、私の場合は入社前の面接でオンライン環境に不安があることを伝えていたため、チームの方が朝会だけでなく夕会も設けてくれました。そのおかげで、会話や相談のタイミングがたくさんあり、安心して仕事に取り組めています。
- 中道
私はプロジェクトマネジメントを担う立場なので、フルリモートだとどうしても「いま各メンバーが何をやっているかわからない」状態になりがちです。オフィスに集まって仕事をしていれば、会話の端々で進捗を把握できますが、リモートだとそうはいきません。とはいえ細かい管理はみんな嫌がるし、僕自身もやりたくない。そのジレンマを感じますね。
- 古田
中道さんのお話には共感します。経理の場合は「誰がどの書類をいつ処理しているか」が見えにくい点がネックでした。特に経理は毎月の決算業務など、期日のある重要な仕事が多いため、期日ギリギリになってまだ終わっていないことが発覚すると、チーム全体に大きな迷惑がかかります。そのため、この「見えづらさ」はかなり課題に感じました。
ーその課題をどのように乗り越えていますか?
- 古田
私は、Backlogでタスク管理を徹底して「誰が」「いつまでに」「どの書類を処理するか」を明確にし、進捗を更新しています。リモートだからこそ、Backlogにすべて情報が集約されるわけで、今はむしろオフィス勤務よりも進捗状態が分かるようになりました。
- 中道
分かります。ヌーラボではBacklogでの情報共有が基本なので、自分が今どんなタスクをしているのかがオープンに見えるようになっています。これは単なる進捗報告ではなく、チーム全体でお互いの動きを把握し合えるメリットもありますね。また、自分のチームでは毎朝朝会を行い、「今週の目標」や「今日のタスク」を各自が宣言し、問題が発生したらすぐにオンラインで集まって議論することにしています。離れているからこそ、こまめにコミュニケーションを取るようにしていますね。
- 史
私はすべてのコミュニケーションを「リアルタイムではないこと」を前提に組み立てています。例えば、時差のあるメンバーに何か相談をするときは「これについてどう思う?」といった曖昧な投げかけではなく、「何が問題で、どういう判断をしてほしいのか」を詳しく書き残します。これにより、何往復もやりとりが発生しないようなコミュニケーションを意識していますね。
しっかりテキストコミュニケーションができれば、世界各地の優秀なメンバーと一緒に仕事ができて、日本だけで生み出せないようなアイデアが生まれる可能性もあってワクワクします。
- 榎本
チームメンバーとはさまざまなミーティングで雑談する機会が多いのですが、それ以外のメンバーともコミュニケーションを取りやすくするために、ヌーラボの「オフィスギャザリング」や「部活動」を活用しています。オフィスギャザリングは四半期に一度ほど、所属するオフィスに集まって交流できる制度で、違う職種のメンバーと直接会うことができます。
部活動は、完全リモートの人でもオンラインで参加することができます。意外とそのようなオフの活動から仕事のアイデアが生まれることも多いんですよね。
「成果」にこだわるからこそ
生産性が上がる
ーリモートワークはモチベーションを保つのが難しい印象があります。どのように工夫されていますか?
- 中道
ぶっちゃけ、私は「家だとついサボってしまう」タイプなんですよ(笑)。そのため、あえてタスクとゴールをオープンに共有することでモチベーションを高めています。朝会で「今日やること」を宣言したら、自分を律する意味でも「この時間までに終わらせるぞ」となるんですよね。仕組みさえ整えれば、生産性は下がらないどころか、上がる場合もあると思います。
- 史
私の場合はあえて「サボってもいい」と割り切りますね。私は「パーキンソンの法則」に共感しており、出社勤務では業務量が少なくても勤務時間いっぱいまで働いているように見せたり、不要な業務を水増ししたりするケースが多いと考えています。フルリモートは、そうした無駄を削ぎ落とす良い機会です。
だからこそ、本当に必要なタスクを見極め、期限内に確実に終わらせることを重視しています。その上で仕事を効率的に進められていれば、「ついサボってしまう」という罪悪感を感じる必要はないと考えています。
- 古田
経理の仕事は、基本的に「締め切り厳守」です。もし期限に間に合わなければ、取締役会での報告ができなくなったり、他部門が予定通りに動けなくなったりしてしまう。なので、Backlogの課題で「誰が」「いつまでに」「どのタスクを行うか」を明確にし、進捗を可視化しています。
オフィスに集まっていた時代は、「隣の席に声をかければすぐわかる」とはいえ、一人ひとりの進捗はブラックボックスになりがちでした。今はリモートだからこそツールにすべて情報が集約され、むしろオフィス勤務よりも進捗の可視化が進んだと感じています。
ーリモートワークをする中で、ヌーラボならではだと思う点はありますか?
- 史
リモートワークを成り立たせるには、「結果を出せれば、そのプロセスは問わない」という文化が大切だと思います。例えば、何かの意思決定や相談に対して、必ずしも机に座っている必要はないし、散歩しながら考えてもいい。結局、会社が求めることは最終的に成果を出すことなので、プロセスはガチガチに管理しないという考え方がヌーラボにはあります。
- 中道
付け加えるなら、情報共有が自然と行われる仕組みをつくることですね。わざわざ「共有しよう」と思わなくても、仕事をする中で自然と他のメンバーに伝わるようにする。そういった文化が根付いているのがヌーラボの特徴だと思います。
業務以外の関わりが
仕事のしやすさにもつながる
ーこれはあってよかったと思う制度や取り組みはありますか?
- 中道
私は「部活動」がすごく好きで、「読書部」に所属しています。読書部では、月に1回 「ビブリオバトル」といって、自分の面白いと思う本をプレゼンする大会が開催されています。普段はどうしても仕事で関わる人とコミュニケーションを取る機会が多いです。でも、部活動があるから普段一緒に仕事をしない人とも話せたり、趣味の共有ができたりして助かっています。榎本さんとは部門は違いますが、読書部でしょっちゅう話しますよね。だから榎本さんには気軽に質問できます。
- 榎本
確かに、中道さんとは仕事でも話しやすいですね。私はオフィスギャザリングのほかに、ヌーラボ本社で開催されるイベントにもよく参加します。そうした場を通して、普段関わりが少ないヌーラボのメンバーとも自然に交流できるので、ちょっとした依頼や相談がしやすくなるんですよね。
- 史
私は「Small Talk」をきっかけに、社内にルービックキューブ好きがたくさんいることを知って、「ルービックキュー部」を立ち上げました。最初はちょっとした雑談から始まったのですが、こうした緩やかなつながりが生まれるのもヌーラボらしいなと感じます。
- 古田
僕はあまり制度を使いこなしていないタイプですが(笑)、全社集会やオフィスギャザリングはいろんな部門の人を知るいいチャンスですね。この前お話したときは、中道さんが車についてとても詳しいことを知って驚きました。こういう雑談の積み重ねが、リモートワークの中でも人間関係を円滑にしてくれると感じます。
- 中道
だからこそ、個人的には拠点を越えてメンバーと会える機会がもっと増えたら嬉しいですね。例えば、全社集会ほど大規模でなくても、もっと気軽に他の拠点のメンバーと直接交流できる機会があったら、よりチームのつながりが強くなると思います。リモートワークが当たり前になった今だからこそ、こうしたつながりを生む仕組みが、ますます大切になってくるはずです。そんな取り組みを、これからのヌーラボにも期待しています。
他のインタビュー記事を見る

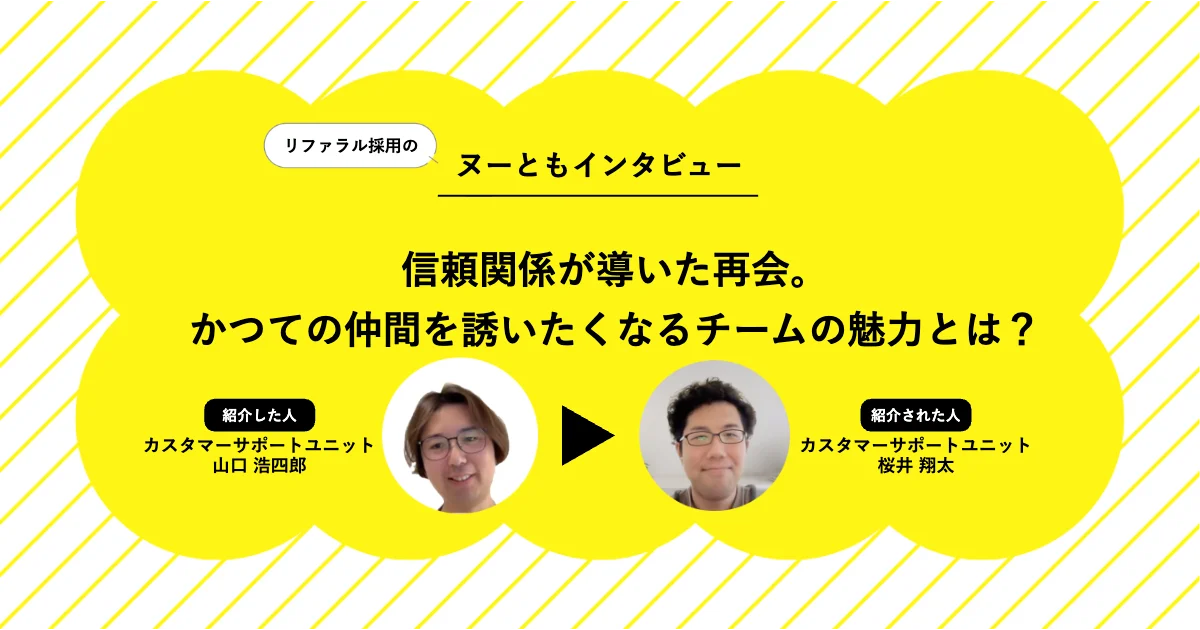
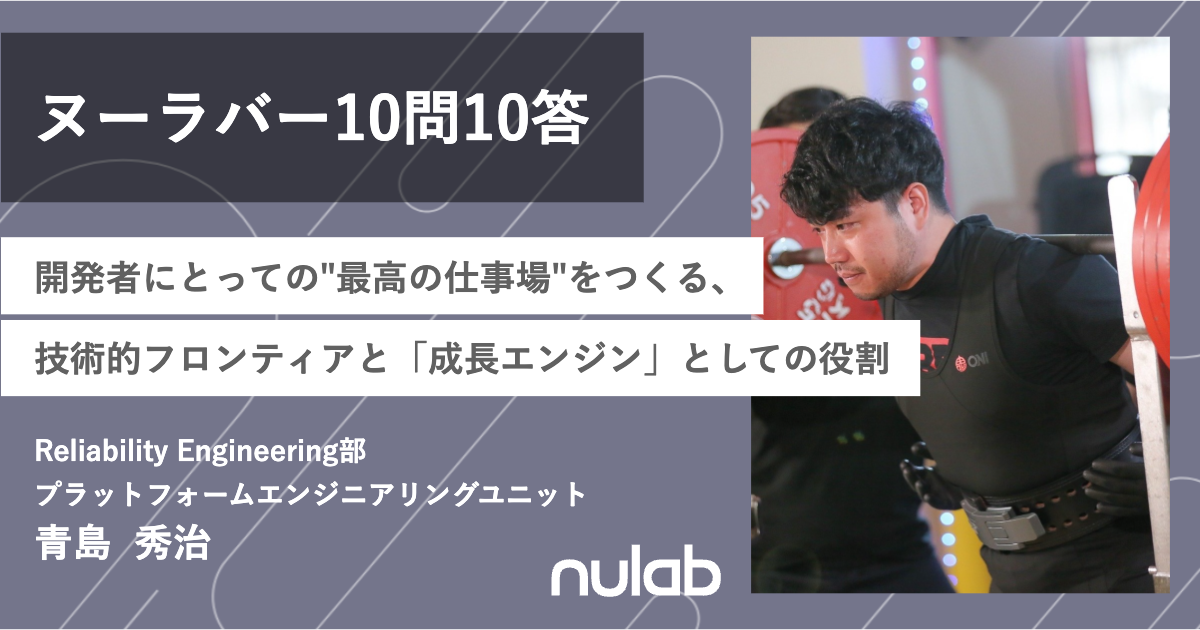
青島 秀治