サービスの価値を高めるヒントは、ユーザーコミュニティの中にある
目次

ヌーラボはユーザーコミュニティやイベントを通じて積極的に外部との接点をつくり続けています。なぜそこまで「外とのつながり」を重視するのでしょうか?
プロダクトマネージャー、カスタマーサポート、カスタマーサクセス、テクニカルサポートエンジニアの4名に、ヌーラボが「外とのつながり」を大切にする理由、コミュニティを通して今後どんな価値を提供していきたいのかを語り合ってもらいました。
サービスの方向性を決める役割として、ユーザーの声を聞きながらBacklogの開発を主導。プロダクトマネージャーとして、機能改善のためのユーザーインタビューやデータ分析を行い、より使いやすいサービスづくりに挑戦している。
ヌーラボの全サービスのお問い合わせ対応を担当。ユーザーから寄せられる相談やフィードバックをもとに、サービスの改善提案やサポート体制の強化に携わる。問い合わせしやすい環境づくりにも力を入れている。
ユーザーの導入支援や活用促進を担当し、スムーズにサービスを使いこなせるようサポート。セミナー開催やデータ分析を通じて、ユーザーの成功体験を増やす仕組みづくりに取り組んでいる。
テクニカルサポートエンジニアとして技術的なお問い合わせ対応や不具合調査を担当。カスタマーサポートと連携しながら、技術的な課題を解決し、ユーザーが安心して利用できる環境を整えている。
「文通相手と初めて会えた気分」
ユーザーコミュニティは新発見の場
ーヌーラボはユーザーコミュニティが活発だと聞いています。具体的にはどのようなイベントがあるのでしょうか?
- 吉澤
Backlog以外にもCacooのユーザーコミュニティ「Cacoo Connect」もあります。また、「Geeks Who Drink」「DAIMYO Meetup」といったエンジニアの参加者を中心としたイベントもありますね。話し合うテーマは最新技術や採用の話などさまざまです。
- 蛭田
それでいうと、カスタマーサポートとして働く方に特化したコミュニティ「さみっぷ!」も運営しています。それ以外にもヌーラボではさまざまなイベントを開催しています。
ー皆さんはどれくらいイベントに参加されていますか?
- 吉澤
イベントへの参加は強制ではないですが、多くの社員が積極的に参加しています。私自身、2024年にBacklogのプロダクトマネージャーになってからは関東圏で開催される「JBUG」には全部参加しています。
- 原
東京で開催されるイベントには、カスタマーサクセスチームやセールスチームのメンバーが必ず誰かしら参加しています。私自身も東京在住ですが、先日福岡に帰省した際にちょうど「Geeks Who Drink」が開催されていたので、飛び入り参加しました。年に一度の大規模イベント「Backlog World」には、東京所属のメンバーだけでなく、福岡や京都のメンバーを含め30人以上の社員が参加していました。
- 立石
私は家庭の事情もあり、今はなかなか参加できていないのですが、以前はユーザーコミュニティの勉強会やエンジニア向けのイベントにも参加していました。

ー印象に残っているエピソードはありますか?
- 蛭田
「Backlog World」に参加した際、たまたま普段お問い合わせしてくださるお客さまとお話しできたことです。普段のやりとりはメールやチャットなどのテキストベースですが、顔を合わせて直接声を聞くことで、お客さまの温度感や感情が伝わってきて嬉しかったです。「文通相手と初めて会えた」みたいな感覚になりました(笑)
また、イベントだとちょっとしたことでも気軽に聞ける環境なので、お困りごとの背景まで詳しくヒアリングでき、「こんな解決策はいかがですか?」という提案ができたことも印象的でした。
- 原
そういった体験は結構ありますよね。「JBUG」のイベントでは、解約されたお客さまが来てくれることもあります。その出会いがきっかけで、改めてオンラインで解約の理由をヒアリングさせてもらえたんです。私たちカスタマーサクセスは解約率の低減もミッションになりますが、解約理由はヒアリングやアンケートだと本音を引き出せなかったり、そもそも答えてもらえなかったりという課題があります。だからこそ、コミュニティで本音で話してくれる方々と出会えてすごくありがたかったです。
- 立石
ユーザーさまが集まる勉強会で、具体的なBacklogの使い方を共有してもらったことが印象に残っています。Backlogの運用方法は企業や個々人でも大きく異なるため、勉強会に参加すると「この機能はこう工夫して使っています」といった事例を知ることができるんです。
以前カスタマーサポートの業務も担当していた際、お問い合わせ対応の中で「既存の機能では対応が難しい」と感じるケースがありました。ですが、勉強会でユーザーさまの工夫を聞いていたおかげで、具体的なアイデアを提案することができました。
- 吉澤
私は「イチ推し機能」を教えてもらえる瞬間です。普段、私たちは「どこが使いづらいか」というマイナスの声ばかりを集めがちで、「何が好きなのか」という声を聞く機会は実は少ないんです。サービスをつくる側からすると「まだまだできていない」と思いがちですが、例えばBacklogのスター機能(※)のような、私たちが当たり前だと思っている機能に対して「この機能が好き」と言っていただけると、改めてサービスの価値を再認識できるし、純粋に嬉しいですよね。
※Backlog上の課題やコメントに対し、感謝の気持ちを伝える機能。

ユーザーの声を素早く形に
ーユーザーから得られた声は、実際にどのように活用されているのでしょうか?
- 原
主に2つの方法で活用しています。ひとつ目は、導入後の使い方に迷われているお客さまへ向けて「先輩ユーザーの声や工夫」として紹介しています。実際に使っているからこその悩みや工夫にはリアリティがあり、特に同業種のお客さまの事例は、具体的なイメージを持っていただきやすいです。
もうひとつは、サービスの改善に生かすための社内フィードバックです。具体的には、毎週金曜日に「Backlogあれこれ会」という会を開催し、ユーザーさまからの要望やフィードバックをプロダクトマネージャーやエンジニアに共有しています。フィードバックは、カスタマーサクセスやカスタマーサポートから共有するものもあれば、ユーザーさまがウェブサイトに直接投稿してくれるものもあり、その量は非常に多いです。こうした声は、社内チャットツールのフィードバック専用チャンネルでも随時共有されています。
- 蛭田
ヌーラボはチーム間の垣根が低く、フィードバックの共有をスムーズに行える環境があると思います。「ちょっとミーティングいいですか?」とチャットツールで声をかければ、すぐにオンラインで集まって話せます。
例えば、最近原さんと一緒に推進しているプラン移行のプロジェクトに関連して、どうしても機能の強化が必要になり、吉澤さんに相談して追加の機能実装をお願いさせてもらいました。このシームレスさは、ユーザーさまにとっても自分たちの声がサービスに反映されやすいというメリットがあると思います。
- 立石
テクニカルサポートの立場からすると、イベントなどでユーザーさまのお困りごとに直接触れることで、より実効性の高い解決策を提案できます。それは職種に関わらず社員として共有できることだと思っていて、チームが分かれていても、「ユーザーさまにとって何が最善か」という共通の視点で議論できていると感じます。
- 吉澤
立石さんに共感します。ユーザーさまの声を通じて、自分のようなプロダクトマネージャーが想定していなかった使い方や課題が見えてくることが多いんです。例えば、チーム間のタスク管理だけでなく、個人の作業管理ツールとして使われているケースもあり、それが機能改善のヒントにつながることも多くあります。
- 原
少し話が逸れますが、最近嬉しかったエピソードがあります。Backlog上でユーザーさまにヒアリングの協力を募集したのですが、約2週間で25件もの応募が集まったんです。他の会社だとなかなかここまでスムーズにヒアリングのアポイントを取れたことがなかったので、正直驚きました。ヒアリングでは、ユーザーさまから「この機能が欲しい」といった要望だけでなく、「お世話になっています」という温かいコメントまでいただき、励みになりました。

ユーザーとヌーラボ、ひとつのチームでサービスを高めていく
ーコミュニティを通して、ユーザーに今後どのような価値を提供していきたいですか?
- 原
ヌーラボのユーザー同士をもっとつなぎ、互いの経験やノウハウを共有いただける場づくりをしていきたいです。それができれば、発信する側も「誰かの役に立てた」という喜びがあり、探している側も「すぐに必要な情報が見つかる」というメリットが生まれます。そんな化学反応が自然と起きる場をつくっていきたいですね。
- 吉澤
原さんの話にあったようにユーザー同士の関係構築は重要だなと感じます。サービス開発の視点で言えば、そういったユーザーのつながりを促すような機能が実装できれば面白いだろうな、と思います。
- 蛭田
カスタマーサポートの立場からすると、イベントやコミュニティを通じて、実際にどんなメンバーがサポートしているのかを知っていただくことで、ヌーラボにより親近感を持っていただけたらと思います。

ー今後、コミュニティを通じてどのような価値をユーザーに提供していきたいですか?
- 原
リアルイベントだけでなく、なかなか声を上げづらい「サイレントユーザー」の方々の意見も拾っていきたいと考えています。実は最近、オンラインコミュニティ「bラボ」がリリースされ、距離や環境の制約でイベントに参加できない方の声を集められる場ができました。今後は、オンラインでの投稿やユーザーのログデータからも、多くの「声なき声」を拾いたいと思っています。
Backlogを使っているユーザー全体をひとつの大きなコミュニティと捉えると、データから見える使い方の傾向なども、立派なフィードバックですよね。より多くのユーザーさまからのフィードバックを集めてサービスの進化につなげていきたいです。
- 蛭田
カスタマーサポートとしては、イベントやコミュニティを通じて「サポートの顔が見える」ことも重要だと考えています。実際にどんなメンバーが対応しているのかを知っていただくことで、ユーザーさまがより気軽にお問い合わせしやすくなったり、安心感を持ってもらえたりするのではないかと思っています。こうした信頼関係を築ける場を、今後も大切にしていきたいですね。
- 吉澤
ヌーラボのサービスは創業者の想いから生まれ、私たちから世の中に訴求していく「プロダクトアウト型」でスタートしました。ですが、今では多くの方に使っていただくようになり、ヌーラボで想定する使い方だけではカバーしきれない広がりを見せています。
そこで重要になってくるのが、お客さまが何に困っているのかを知ることや、その声と私たちヌーラボが目指したい方向性を上手くかけ合わせていくことです。この令和の時代に見合った、さらにはその先を見据えたサービスを提供していくためには、コミュニティを通じてユーザーさまの声を直接聞き、「ユーザーさまと一緒に」サービスを成長させていくことが大切だと感じます。
- 立石
私たちが最終的に目指しているのは、カスタマーサポートやテクニカルサポートがいなくても、ユーザーの皆さまが自然と使いこなせるサービスをつくることです。コミュニティは、サービスのさまざまな使い方の共有の場であると同時に、ユーザーさまの困りごとや要望を直接聞ける機会です。先ほど原さんも言及されていた「使いこなせない」という声などの課題を吸い上げ、ユーザーの皆さまがサポートなしでもサービスを使えるようにしていきたいです。

他のインタビュー記事を見る

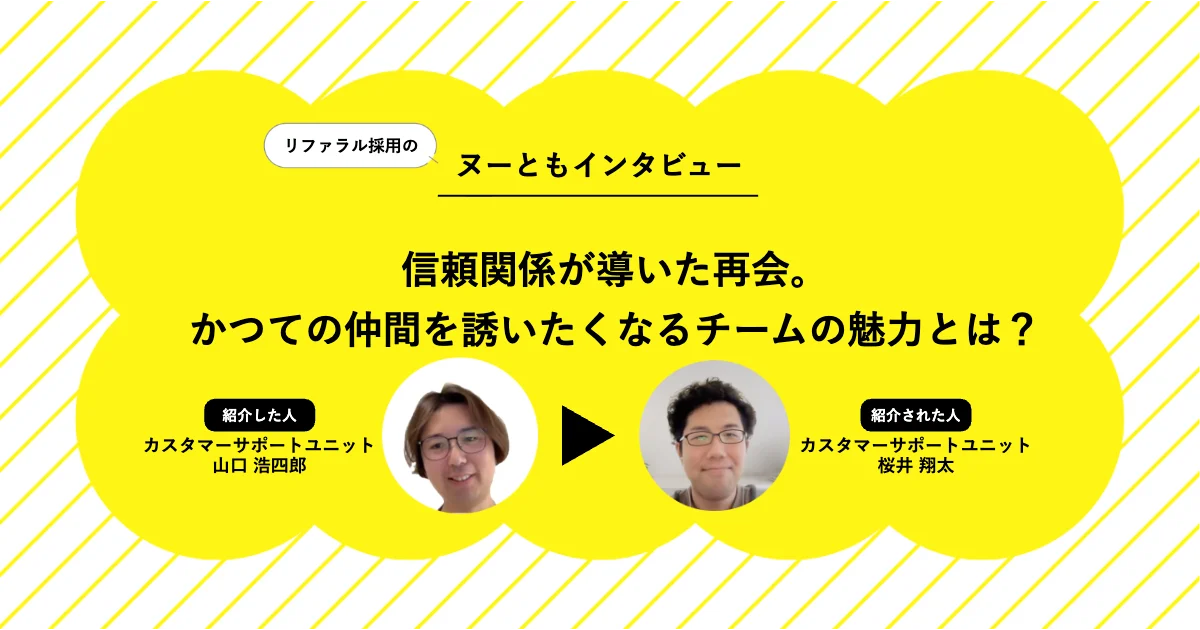
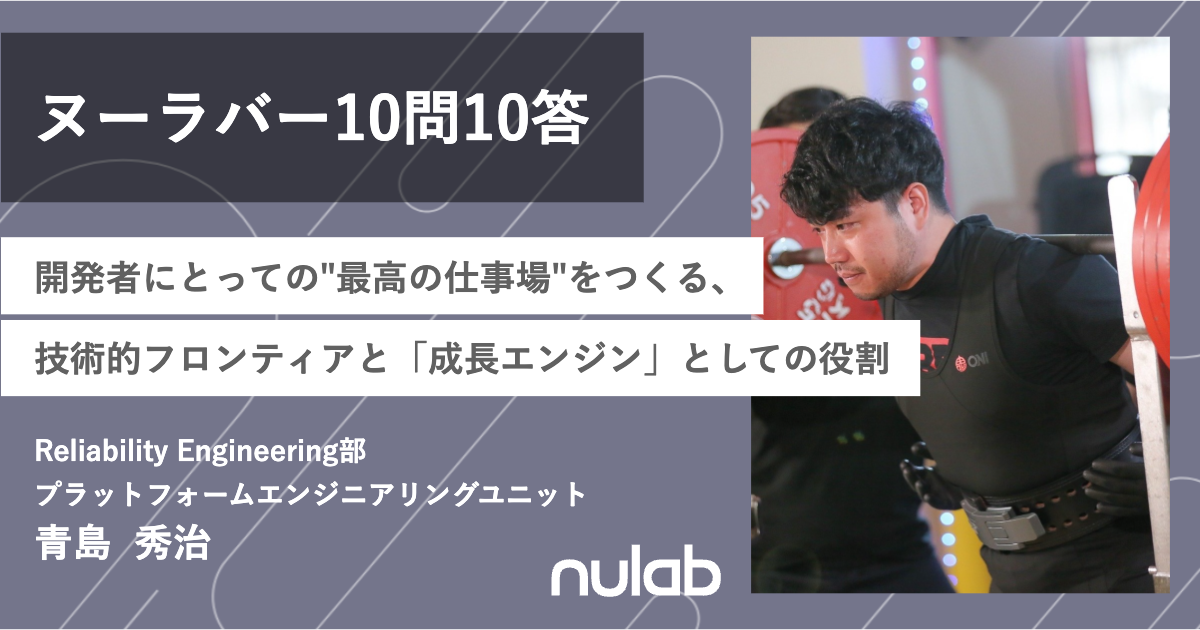
青島 秀治